「肩が前に出ている気がする」「姿勢が悪いとよく言われる」
そんな方は、もしかすると“巻き肩”になっているかもしれません。
実はこの巻き肩、不良姿勢による肩こりや首こりだけでなく、将来的に五十肩を引き起こすリスクも高めてしまうのです。
本記事では、巻き肩の特徴・原因・影響から、五十肩との関係性、そして予防・改善のための具体的な方法までをわかりやすく解説します。
巻き肩とは?猫背との違いも知っておこう
巻き肩とは、肩が体の前方に突出し、肩甲骨が外側に開いた状態のこと。
胸の筋肉(大胸筋や小胸筋)が縮こまって固まり、肩周囲の骨格の位置がずれてしまうのが原因です。
一方、猫背は背骨(胸椎)が丸まり、頭部が前に出る姿勢全体の崩れを指します。
巻き肩は肩関節まわりに特化した不良姿勢で、放置していると猫背を誘発する要因にもなります。
巻き肩の主な原因
巻き肩は、日常の生活習慣が大きな要因です。
- 長時間のスマホ操作やパソコン作業
→ 肩が前に引っ張られる姿勢が定着 - 横向き寝のクセ
→ 上半身の重みで肩が前方へ圧迫される - 姿勢のクセ(なで肩・反り腰)
→ 体幹のバランスが崩れ、肩だけが前に
このような生活が積み重なることで、気づかぬうちに巻き肩が定着してしまいます。
巻き肩が引き起こす身体への影響
巻き肩になると、肩関節だけでなく、体全体に以下のような影響を及ぼします。
- 首こり・肩こり・頭痛
- 姿勢の悪化(猫背・反り腰)
- 呼吸が浅くなる(肋骨の可動制限)
- 自律神経の乱れ(疲れやすい・眠りが浅い)
そして、これらが慢性化すると、五十肩のリスクも高まってくるのです。
巻き肩と五十肩の関係性とは?
1. 可動域の制限 → 関節の炎症へ
巻き肩の状態では、肩甲骨が外に広がり、肩関節の動きが制限されます。
この“可動域の狭まり”が肩へのストレスを蓄積し、関節の癒着や炎症=五十肩の引き金となるのです。
2. 血流の悪化 → 炎症が治りにくい
巻き肩によって胸や肩前面の筋肉が緊張すると、血流が悪くなりやすくなります。
この状態が続くと、修復が追いつかず、慢性的な微小炎症が肩周囲に蓄積され、五十肩を招きます。
3. 自覚のない長期的な負担 → 突然の激痛に
巻き肩は、痛みが出にくいため放置されやすいです。
しかし、知らず知らずのうちに肩関節への負担が積み重なり、**40〜50代で突然「肩が上がらない」「激痛が走る」**といった五十肩の症状として現れることがあります。
巻き肩・五十肩を防ぐためにできること
ストレッチで肩甲骨の動きを取り戻す
以下のストレッチを日常的に取り入れることで、肩周りの柔軟性が戻り、巻き肩・五十肩の予防になります。
✔ 胸筋ストレッチ
壁に手を当て、反対方向に体を回すことで、縮まった胸の筋肉をほぐします。
✔ 肩開きエクササイズ
後頭部に手を当て、肘を開いて胸を張ります。肩甲骨を寄せる意識を持つとより効果的です。
✔ 肩甲骨の前後運動
手を背中と前方で組み、肩甲骨を「寄せる・広げる」を交互に行います。
無理なく、毎日少しずつ続けることが大切です。
改善が難しいときは、専門的なケアを
セルフケアではなかなか改善が見られない方は、当院での施術がおすすめです。
- 胸や肩前面の筋膜リリース
- 巻き肩を改善するための骨格調整
- あなたの姿勢や生活習慣に合わせたストレッチ指導
こういったアプローチを受けることで、根本的な改善が見込めます。
まとめ:巻き肩のうちにケアすることが、五十肩の予防になる
五十肩は「突然起こる肩のトラブル」と思われがちですが、実はその予兆は日々の姿勢や筋肉の状態に隠れています。
巻き肩は、五十肩の“入り口”。
気づいた今が、改善のベストタイミングです。
当院では、巻き肩の状態をチェックし、筋・骨格の調整などを組み合わせた施術で、無理なく本来の姿勢に戻していくサポートをしています。
「最近、肩が前に出ている気がする…」
「肩の動きがスムーズじゃない…」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。



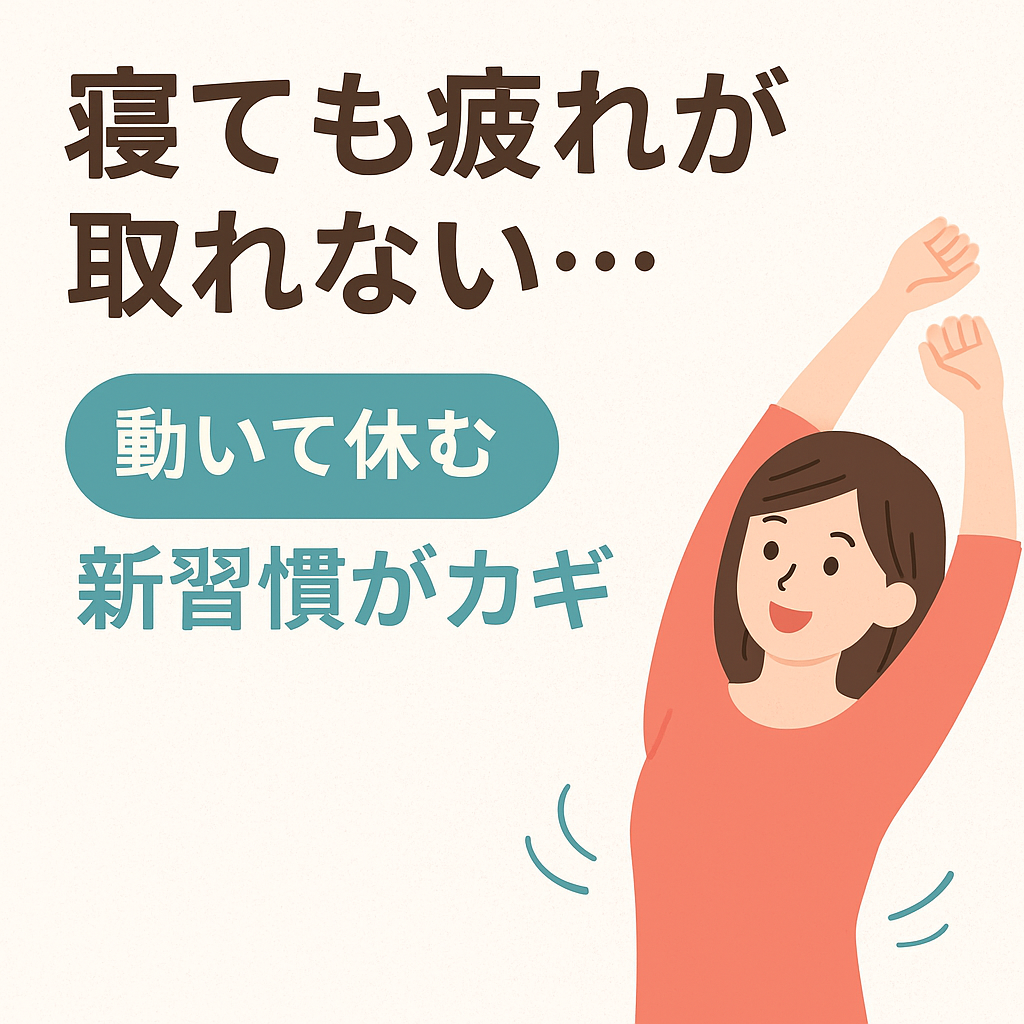
コメント